「As Is / To Be」分析をしたのはいいものの、現場の業務が1mmも変わらない……という悩みは、多くのDX担当者や管理者が直面する最大の壁です。
業務改善の現場では、現状(As Is)を分析し、あるべき姿(To Be)を書き出し、業務プロセスとして新たに落とし込む場面が少なくありません。しかし、To Beを書き出して理想を確認できたのは良いものの、理想を実現させるための業務への落とし込みと定着で難航するケースが多く、結果「理想」で終わってしまい、現状の改善をまた改め直すということが多くあります。
本記事では、そんな理想となる「To Be」を実現するためのサポート役として、普段の業務への落とし込みや、実効力のある管理体制を確保する「octpath」で仕組化する方法をお伝えしています。
現状分析(As Is)と理想(To Be)の策定後に発生する「実行の乖離」

多くの企業がコンサルティングや社内会議を経て、立派な「新業務フロー図」を作成します。しかし、その図面が完成した瞬間が、実は「改善の停滞」の始まりであることも珍しくありません。
いざ実際の運用フェーズに移行すると、策定したルールが守られない、あるいは以前のやり方に逆戻りするといった、理想との「乖離」が多くの組織で発生します。
この乖離を放置すると、改善活動そのものに対する不信感が現場に広がり、組織全体の変革意欲を削ぐことになりかねません。
業務改善プロジェクトが実行フェーズで停滞する主な要因
なぜ、改善案や新しいプロセスが実行フェーズで停滞してしまうのでしょうか。それは管理者/現場担当者だけに問題があるわけではありません。その原因は主に以下の3点に集約されます。
①「やり方」が周知されるだけで「強制力」がない
新しいフローがメールやチャットで周知されても、忙しい現場は「慣れた旧来のやり方」を優先してしまう。
②マニュアルの参照コストが高い
至るところで「新しい手順は○○のマニュアルを参照してください」などと、業務の最中にマニュアルを探しては業務に戻るなどの手間が生じてしまう。
トラブルが発生した際や不明箇所がある場合なども誰に聞けばいいのか、どのマニュアルを参照すればいいのか分からない。なども生じてしまうと、結局自己流やその場しのぎのやり方に戻ってしまう。
③進捗が可視化されないため、形骸化に気づけない
今どこでどの業務が止まっており、誰が担当しているのかが管理者に分からず、全体進捗の把握や遅れの発見が遅れてしまう。
策定された「To Be」を現実の業務に定着させるためのIT活用
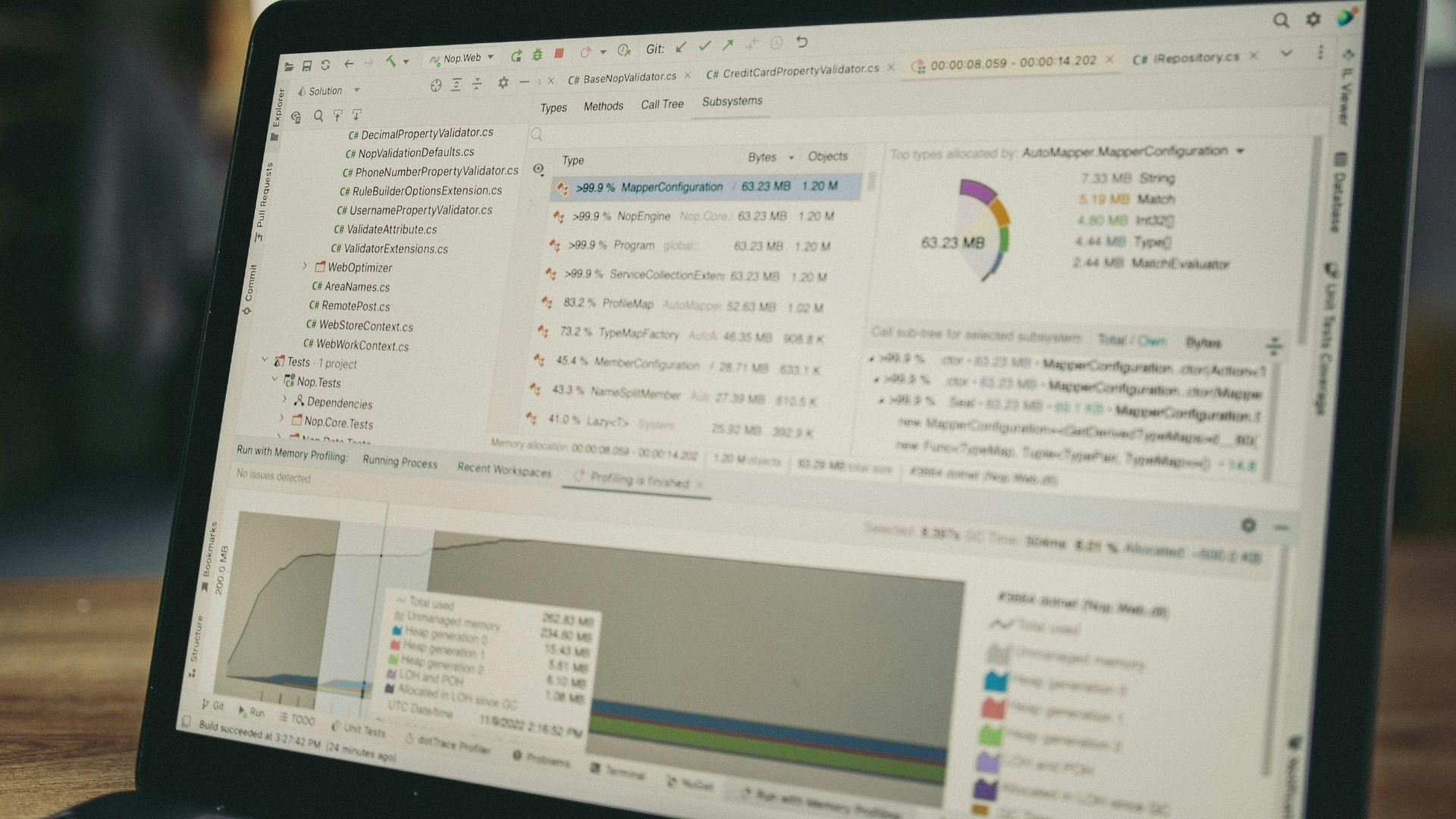
理想(To Be)を定着させるためには、現場の「意識」に頼るのではなく、「それしかできない状態」をシステムで作ってしまうことが最短ルートです。
意識改革ではなく、システム的なプロセスの刷新による移行
組織を変えようとする際、真っ先に「社員の意識を変える」ことを目標に掲げるのは、定着の難易度を著しく高める原因となります。意識という実体のないものを変えるよりも、ITを活用して物理的にプロセスを刷新すると、結果として移行はスムーズに進みます。
octpathのようなプロセスマネジメントツールを導入すると、業務の「入り口」から「出口」までがデジタル上のレールとして敷かれます。作業者はそのレールに沿って入力を進めるだけで、自然と「To Be」を体現した動きになります。これにより、教育コストを最小限に抑えながら、初日から理想のクオリティで業務を遂行することが可能になります。

ITツールによって「新しい手順に沿わなければ業務が完了しない」仕組みを構築することで、現場は心理的な抵抗を感じる間もなく、自然と新しいプロセスへ順応していくことが可能になります。システムがガイド役となることで、迷いや誤判断の余地を物理的に排除できます。
octpathを用いた新プロセスの強制実装と効果測定

octpathは単なる管理ツールではなく、定義された「To Be」を日々の実務として確実に稼働させるためのツールとして機能します。
【octpathとは?】属人化を根本解消し、業務全体を標準化するSaaSの全貌
2025/10/24理想のフローをデフォルトのワークフローに設定し、旧プロセスへの逆戻りを防止
octpathを活用することで、以下の仕組みを瞬時に構築できます。
■業務状況と紐づいた「動くマニュアル」としてのフロー実装
定義したTo Beフローをそのままoctpathのステップに落とし込みます。各ステップに作業手順やチェックリスト、画像や資料の添付フォームなどを埋め込めるため、フローとマニュアルが一体となり、業務ごとにマニュアルを探す手間が無くなります。
また、octpathでは様々な条件分岐が作成可能で、その時の業務状況に応じて次にやるべきタスクをナビゲーションしてくれます。担当者は必要な情報の入力や確認が完了しない限り、次のステップへ進めない制約をシステム側で担保します。
■リアルタイムな業務進捗の見える化とボトルネックの検知
octpathでは業務新緑を一目で確認できるため、「どこで作業が止まっているか」、「どのステップに時間がかかっているか」がこれまでの管理に比べて一目瞭然になります。
これにより、描いたTo Be自体に無理があった場合も、データに基づいた迅速な再改善と継続的な改善(PDCA)を回すことが可能になります。
こうした制御は、担当者の記憶力や判断のばらつきに依存しない「業務の標準化」を強力に後押しし、旧プロセスへの逆戻りを物理的に防ぎます。
まとめ:分析を価値に変えるための「実装力」の重要性
業務改善の成功は、現場頼りや意識的なものだけではなく、「現場での実装」にかかっています。As IsからTo Beへの移行期は、組織への負荷が高く、脱落者が出やすい危険なフェーズです。
せっかく定義されたTo Beとそれを実現させるプロセスを、単なる「理想の姿」として終わらせず、ITツールを活用した「仕組み化」で、現場が意識せずとも理想を実現できる環境を整えていきましょう。